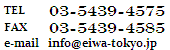★登記の間違いはすぐわかる?★
一般的な登記はシンプルなものが多く、
「何を登記簿に記載すべきか」
ということは、厳密に法律で規定されているため、誰が見ても、完成した登記が正しいか否かの判断ができます。
よって、仮に間違った登記が完成したとしても、その正誤の判断が容易にできます。
では、すべての登記に同じことがいえるのでしょうか。
★全ての登記は同じではありません★
前記のとおり、成果判断の基準が明らかである場合、その正誤判断は明らかとなると申し上げました。
では、すべての登記でもそうなのでしょうか…?
答えは「No」です。
その理由ですが、そもそも登記とは、現実社会で起きた法律関係を公示することが主要目的の一つです。
そして「公示」という性質上、その表記は誰が見てもある程度のことが判断できるような画一性が求められます。
これに対して、その登記の対象となる事実関係は、哲学的表現をすれば、似たような事案であっても実は異なっていて一つとして同じケースはありません。
例えば、前記のシンプルなケースとされる売買であっても、例えば売り主の判断能力が100%完全な状態でなされたというケースもあれば、認知症で判断能力がないとされるケースもあります。このような両極端なケースではないにしても、例えば飲酒をしていて、酩酊とまでは言わないにしても、ちょっと気が大きくなっている状態というケースもありえます。
判断能力が100%かゼロというケースはあまり疑義がないと言えますが、「飲酒状態」という状態はそのような判断能力状況下で行われた行為が有効か否かということは、人によって判断が分かれるところです。
→ある人はこの状態を「有効」と判断するでしょうし、別の人は「無効」もしくは「適切でない」と判断するのではないでしょうか。
ここまでお読みいただいた方は、「最初に書かれたシンプルな登記は誰がやっても同じじゃないのか?」とお考えかと思います。
確かにそうなのですが、厳密に表現すると、
「登記の結果は同じにならなければならない。しかし、登記の客体となる事実関係をどう判断するかは、判断者によって分かれる。その結果として、事実を正しく反映しない登記がなされることが起こり得る。」
ということです。
★登記は万能ではありません。それが如実に現れるのが「信託」登記。★
結局のところ、登記簿の公示能力には限界があるということです。
そして、その点が如実に現れるのが信託登記です。
信託登記の場合、登記簿の一部として必ず、信託目録が作成されます。
信託目録の役割は、信託契約の内容を公示することにあります。
では、この信託目録に何を記載すべきかについて、不動産登記法は以下の事項を記載しなければならないとしています。
1:信託の目的
2:信託財産の管理・運用・処分方法
3:信託の終了事由
4:その他の信託条項
・・・、これだけです。
この信託目録は端的に述べると「この信託は、信託目録記載の内容について制約のある信託である」という役割を担い、対外的には登記の公示機能によりその制約事項を公示し、対内的には登記手続を制約します。
(公示機能の部分は説明を要しませんが)つまり信託目録に記載されている制約どおりに登記手続きを進めなければならないということになります。
例えば、よくある間違いとして信託終了時の信託元本をどのように処理すべきかという点があります。
★当事者の目論見と反する登記結果になる★
最近の信託の利用事例は主に流動化・証券化を目的としたものであるため、信託設定当初は自益信託、信託設定後、受益権を第三者に譲渡するスキームが大半です。
いわば、信託の権利変換機能に着目し、信託をすることにより所有権を受益権に転換し、以後、転々流通させることを目的とするわけです。
このような信託の場合、所有者である受託者の名義は極めて形式的な受動信託といってよく、そのスキームを実際コントロールしているのは受益者(もしくはレンダー)であるといえるため、信託が終了したときの元本受益者は受益者でなければなりません。
(事実ほぼ全ての事例で、信託元本は受益者に交付されると規定されています。)
ですので、このスキームの目的を達するためには、信託目録に元本受益者は「信託終了時点での受益者である」と明記しなければならないのですが、その記載そのものをしていない信託目録が散見されます。
この記載がない場合の法務局の判断・登記手続きはどうなるかですが、
①信託目録に記載がない
②信託法の条文を参照
③委託者に元本交付がなされる
という流れになり、当事者の目論見と真逆の結果が発生してしまいます。
★スキーム・信託法の理解が大切★
では、上記のような性質を有する信託目録に具体的にどのような内容を記載すべきかですが、法律上定められているのは前記1〜4の項目までで、具体的にその中身に何を記載するかは申請人の任意とされています。
つまりスキームに合致した信託目録を作成するためには、ある程度の流動化に関するスキームの理解と信託法に関する理解が必要となります。
換言すると、仮に間違った登記がなされた場合、信託登記に当たっては、スキームや信託法のある程度の知識がないと、その間違いの存在を見抜けないということなのです。
つまり、信託登記では信託目録に「何を記載すべきか」ということが特に大切であるということになります。