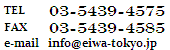★債権調査は難しい★
債権を担保にとるときの注意点は、「債権が目に見えないもの」であることを意識しているか否かにあります。
不動産担保であれば、現地に行けば、その確認ができ、その裏付けを不動産登記簿により行うことができますが、対象が債権の場合、債権が目に見えず、また不動産登記簿のような公示制度もないため客観的な確認ができません。
結局のところ、譲渡人である債務者が「自分は甲宛の金銭債権を保持している」というのであれば、その言葉を「信じるか」「信じないか」ということにいなります。
確かに、債務者の言葉だけを鵜呑みにするのは危険なので、例えば債務者と甲間の取引基本契約書や、甲からの発注書等、何らかの経理証憑書類に基づき確認をとるのが通常です。
そして、そのような書類があったとしても、
「譲渡禁止特約のついた債権ではないのか」
「相手方に反対債権があり、相殺を主張されるような債権ではないのか」
「そもそも弁済等によって債権は消滅しているのではないのか」
といったことの把握が難しいのが実際です。
また、取引形態によっては、そもそも基本契約書等の債権債務の存在を推認させる書類が存在しないというケースもあります。
このような場合、結局、債務者の言葉だけが頼りということになります。
★ぐずぐずしていると後手に回る。思い切って進めることも大切。★
ポイントは、債権調査にどこまで完璧を求めるかということになりますが、弊社の見解としては、ある程度のところで「思い切る」ことが大切と考えます。
その理由ですが、前記のとおり、債権を担保に取るということはその内在的宿命として、どこまで調査しても100%にはならないということがあります。
仮に100%を期するのであれば、第三債務者たる甲に債権の存否を確認するしかありません。
しかし、債権担保の大半のケースは、「譲渡担保」であり、取引先に妙な信用不安を誘起させないため、第三債務者である甲に甲自身が債務者である債権が譲渡担保の対象債権であるということを隠しておくことが通常ですので、甲に債権の存否の確認はできず、100%の確認はできないということになります。
よって、その真偽不明の債権が、譲り受ける債権の中に占める比率がさほど大きくないのであれば、ある程度の調査で切り上げて、速やかに契約締結・登記まで行わないと、ぐずぐずしている間に、競合債権者(租税債権が特に怖い)からの差し押さえ等の妨害や最悪の場合、譲渡人が破産してしまうという事態が生じる可能性がないとは言い切れません。
(譲渡人が破産して債権担保そのものが否認されたらどうするのか?ということも考えられますが、それは破産したときに考えればよいのであって(破産しないかもしれませんから・・)担保に取る前から否認を気にしていては、時期を逸すると考えます。)
★債権譲渡登記のコストは、抵当権等の不動産登記コストに比べれば、ほんの僅か★
また、もし、譲渡人との間で、譲渡担保設定後も優位に交渉を進める立場にあるということであれば、ひとまず、ベターと思える状態で見切りを付け、債権譲渡登記をし、その後にもし誤った登記等が発覚した場合は、その登記だけを追加でやり直せばよいと考えます。
確かに、登記を追加でやり直すことはコストがかかりますが、債権譲渡登記の場合、抵当権等の不動産担保と異なり、どれだけ巨額の極度額の譲渡担保であろうと、登録免許税等の実費自体は、7500円ですることができ、やり直しの登記についても同様です。
(不動産担保の場合、その設定金額の0・4%が登録税として発生します。)
ですので、登記自体のコストは不動産担保と比べれば、かなり低額ですので、「仮に間違ったとしても、その後で正しい登記を行えばよい」という考えで先手を打つ方が債権保全にとっては望ましいと考えますがいかがでしょうか?
大切なのは、「思い切り」をもって「スピーディー」に対応するということにつきます。