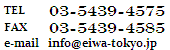★動産の譲渡についても登記ができるようになりました。★
法律の改正により、動産の譲渡も登記対象となりました。
動産の対象に制限はなく、大型機械のような単一動産だけでなく、倉庫在庫のような集合動産の譲渡を登記できるようになりました。
そして、登記をする事で対抗要件を具備することができます。
これまでの民法では動産の譲渡について対抗要件を具備するためには、現実または観念的な「引き渡し」をすることが必要とされていましたが、動産譲渡登記を行えば、この「引き渡し」を行ったものとみなされることになります。
★「登記」でもOK,これまでどおり「引き渡し」でもOK。★
しかし、ここからが紛らわしい話なのですが、「登記」制度ができたというと、これまでの対抗要件具備方法である「引き渡し」が廃止されたのかというお問い合わせをいただくことがあるのですが、そうではありません。
こちらも引き続き有効とされ、どの方法を選択しても対抗要件は具備されます。(もちろん両方行ってもOKです。)
(余談ですが、現実問題として、対抗要件具備方法を登記に限定してしまうと、消しゴム1個を買っただけでも登記をしなければならなくなりますので、これはこれで仕方がないといえます。)
★動産担保のメジャーは「譲渡担保」★
ここで、動産担保の場合の要注意事項として即時取得の問題があります。
動産を担保とする場合、現在の法制度で妥当と考えられる手法は「質権」と「譲渡担保」があります。
そして、実際の商取引で有用として圧倒的に多いのは、「譲渡担保」です。
(質権の場合、成立要件として、担保権者が質物の占有を取得しなければならず、仮に担保対象動産が営業動産である場合、当該動産に質権を設定してしまうと、営業の用をなさなくなってしまうためです。)
換言しますと、債務者の手元に動産を置いておきたいが故に譲渡担保を設定しているといえます。
★債務者が悪さをするのでは?・・・・悩ましい即時取得★
譲渡担保を設定した後で注意しなければならないのが、当該動産に対する第三者の即時取得の成立です。
前記のとおり、債務者の手元に置いておく必要があるが故に譲渡担保を設定するのですが、それは見方をかえると、債務者の手元にあるために、第三者から見れば当該動産は債務者が所有している物と誤認されやすく、そこに債務者が悪意でもって
「この品物は私の物です」
として、第三者と当該動産の売買をし、引き渡し等をしてしまうと、そこで第三者に即時取得が成立してしまいます。
即時取得が成立すると、その反射的効果として法律上の所有者である譲渡担保権者の所有権は喪失されることになります。
★動産登記では債権保全が図れない?★
さて、ここで登記のお話に戻りますが、新しく登記制度が設けられたので、上記の即時取得の問題もクリアできると思われがちですが、そうではありません。
登記はあくまで、これまでの引き渡しと同じ効果があるというだけで、即時取得を遮断する効果はありません。
ですので、登記をした上で、当該動産がある現場にも立て札やプレートなどの明認方法を施して、第三者の悪意が擬制されるようにしなければなりません。
また明認方法を施していても、債務者が害意をもって明認方法を取り外して第三者に売却等をし、第三者に即時取得の要件が備わっていた場合、(債務者の担保権侵害という別の問題は発生しますが)譲渡担保権は消滅することとなります。
つまり、登記をしたからといって債権保全が万全となることではないということを意味します。
★「登記」をする前によく考えて・・・★
ここで話は少し変わりますが、もしお客様から「債権譲渡登記を登記留保にしてよいか」と聞かれれば、(あくまで法的な観点からだけですが)それは「お勧めできません」と答えます。
同様にもし、お客様から「動産譲渡登記を登記留保にしてよいか」と聞かれれば、「お客様のビジネスジャッジにお任せします」と答えます。
その理由ですが、動産譲渡登記の場合、前記のとおり、登記をしたとしても第三者の即時取得を防止することができないので、債権保全が万全になったとはいえません。
そして、通常、動産譲渡担保の対象となる動産というのは営業用動産であったり、販売在庫であったりと、最終・緊急の担保物であるという意味あいが強いといえるのではないでしょうか。
このような性質の動産が担保に提供されたということが登記されると、債務者の信用不安を誘起しないかということを注意しなければなりません。
換言すると、登記をしても債権保全は万全とならないのに、登記をすることにより生じるかもしれないリスクを許容できるかという問題です。
このリスク判断は、法的判断ではなく、「本当にこの債務者は動産譲渡登記から生じるかもしれない信用不安等のリスクに耐えられるか?」というビジネスジャッジであるため、登記をするかしないかは、よくご検討いただく必要があると考えます。